糖尿病・肥満とミトコンドリア呼吸の関係性 ~Agilent Seahorse XFを用いた培養細胞と生体組織の代謝測定~
糖尿病や肥満は過剰な糖や脂質が蓄積することによってミトコンドリア内の電子伝達系で活性酸素種(ROS)量が増加し、ミトコンドリア損傷を引き起こします。その結果、細胞内のミトコンドリア呼吸能力が低下するこ...
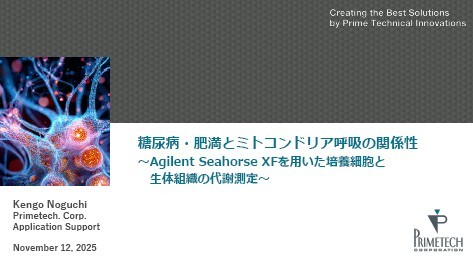
糖尿病や肥満は過剰な糖や脂質が蓄積することによってミトコンドリア内の電子伝達系で活性酸素種(ROS)量が増加し、ミトコンドリア損傷を引き起こします。その結果、細胞内のミトコンドリア呼吸能力が低下するこ...
次世代シーケンサー(NGS)を用いた解析には、全ゲノムシーケンス(WGS)、RNA-seqをはじめとする多様なアプリケーションが存在します。こうしたNGS実験の成功のカギは、ライブラリーの品質にあるこ...

超音波エラストグラフィは、組織の「硬さ」を可視化・定量化することで病態の進行を捉える革新的な手法として、近年注目を集めています。 臨床領域では2000年代から肝線維化のステージングに広く用いられてきま...
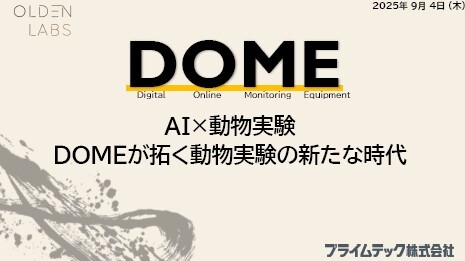
創薬研究開発を含む生命医学研究は莫大なリソースを消費します。例えば新薬を1つ開発するためには、平均して約26億ドルの費用と10年以上の歳月がかかると報告されています*1。また米国では毎年約1億1千万匹...
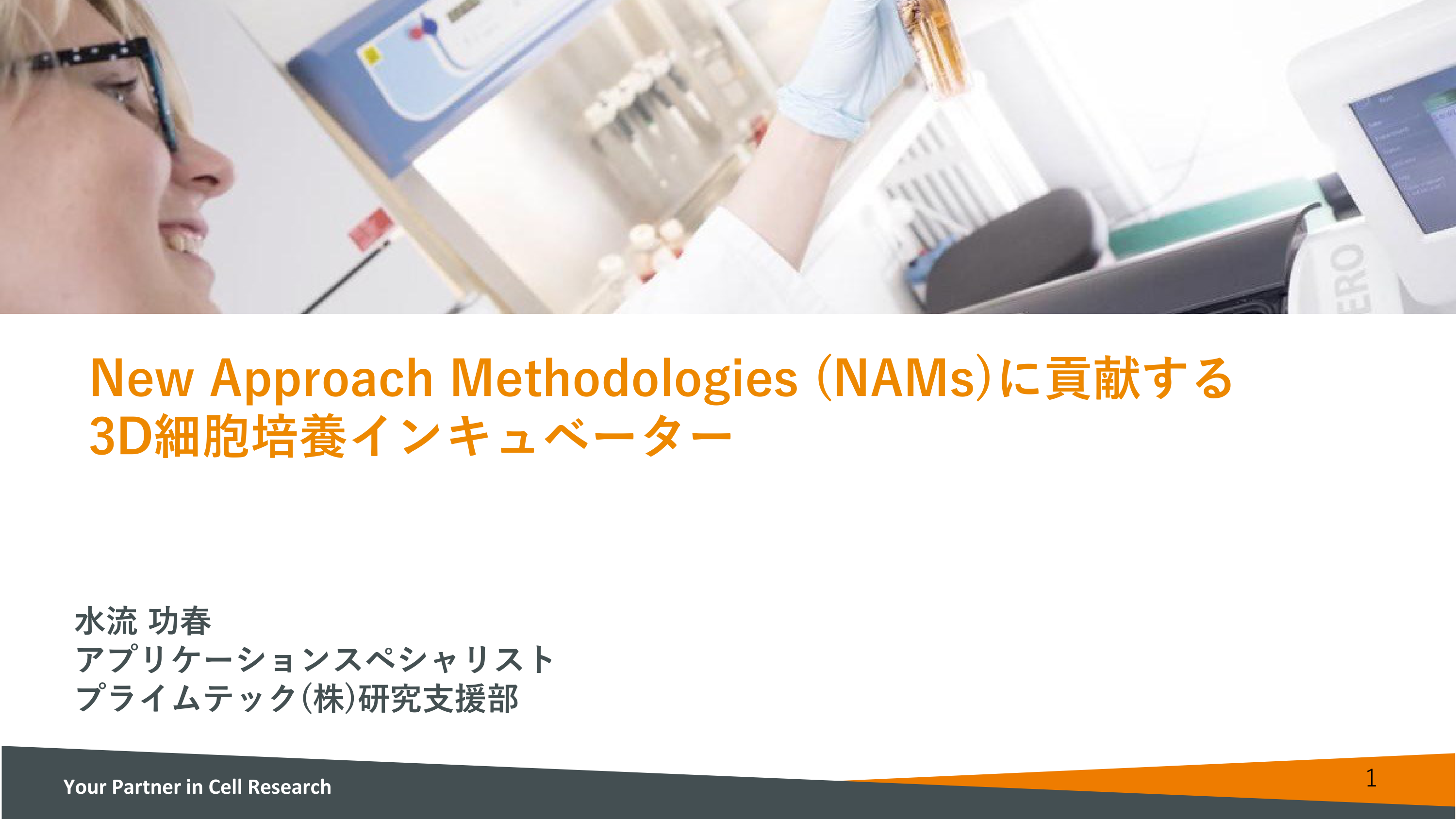
医薬品開発において、より安全で有効な薬剤を迅速に提供するため、ヒトでの予測性の高い評価法、すなわちNew Approach Methodologies (NAMs)の導入が国際的に重要視されています。...

現在の創薬・基礎研究市場で活用されているPET、SPECT、CT、MRIといったin vivoイメージングモダリティは、異なるエネルギーと撮像原理を利用し、実験動物の生体内情報を可視化するさまざまな機...
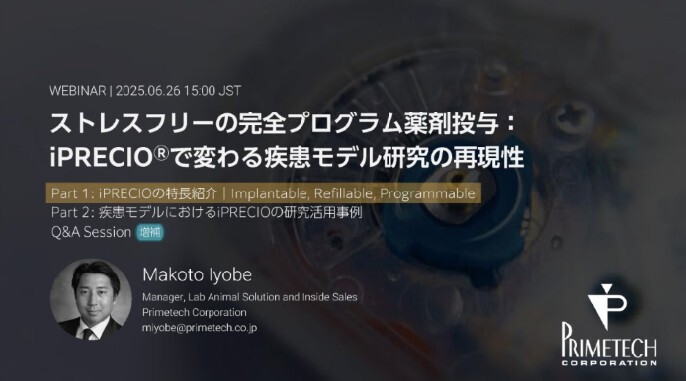
人間の病態を再現したヒト疾患モデル動物は、疾患バイオロジーの理解や治療法開発において不可欠な役割を担っています。とりわけ、モデルの再現性や臨床的妥当性を高めるうえで、薬剤投与レジメンの設計は極めて重要...

メディフォード株式会社・プライムテック株式会社の2社共催による合同ウェビナー。国内外の創薬研究者の方々へ、実験動物における超音波エコー計測技術の最新動向と、その実際をユーザー目線でご紹介しました。
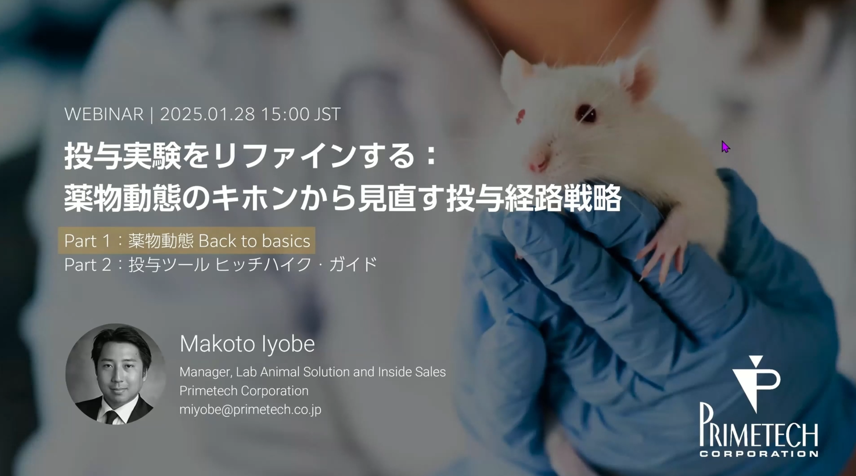
薬剤が本来の効果を発揮するためには「目的の部位に」「適切な濃度で」「充分な時間」とどまらせることが重要です。実験動物への投与経路は多岐にわたりますが、投与する薬剤の体内動態と、投与経路の特徴を考慮して...
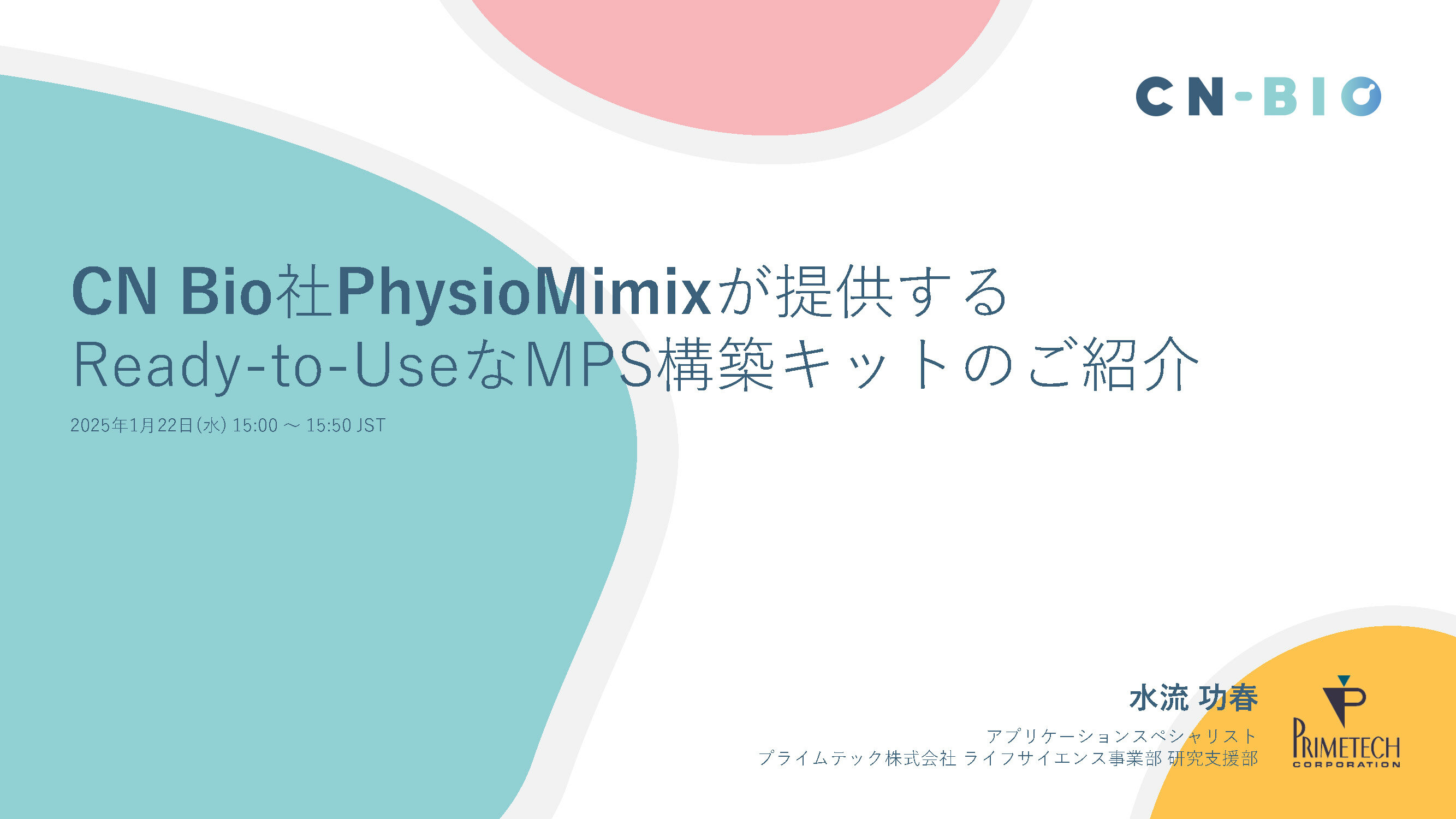
前回のウェビナーでは、CN Bio社が提供するMPS (生体模倣システム)プラットフォームであるPhysioMimixシステムの概要とその有用性についてご紹介しました。続いて本ウェビナーでは、生体内環...
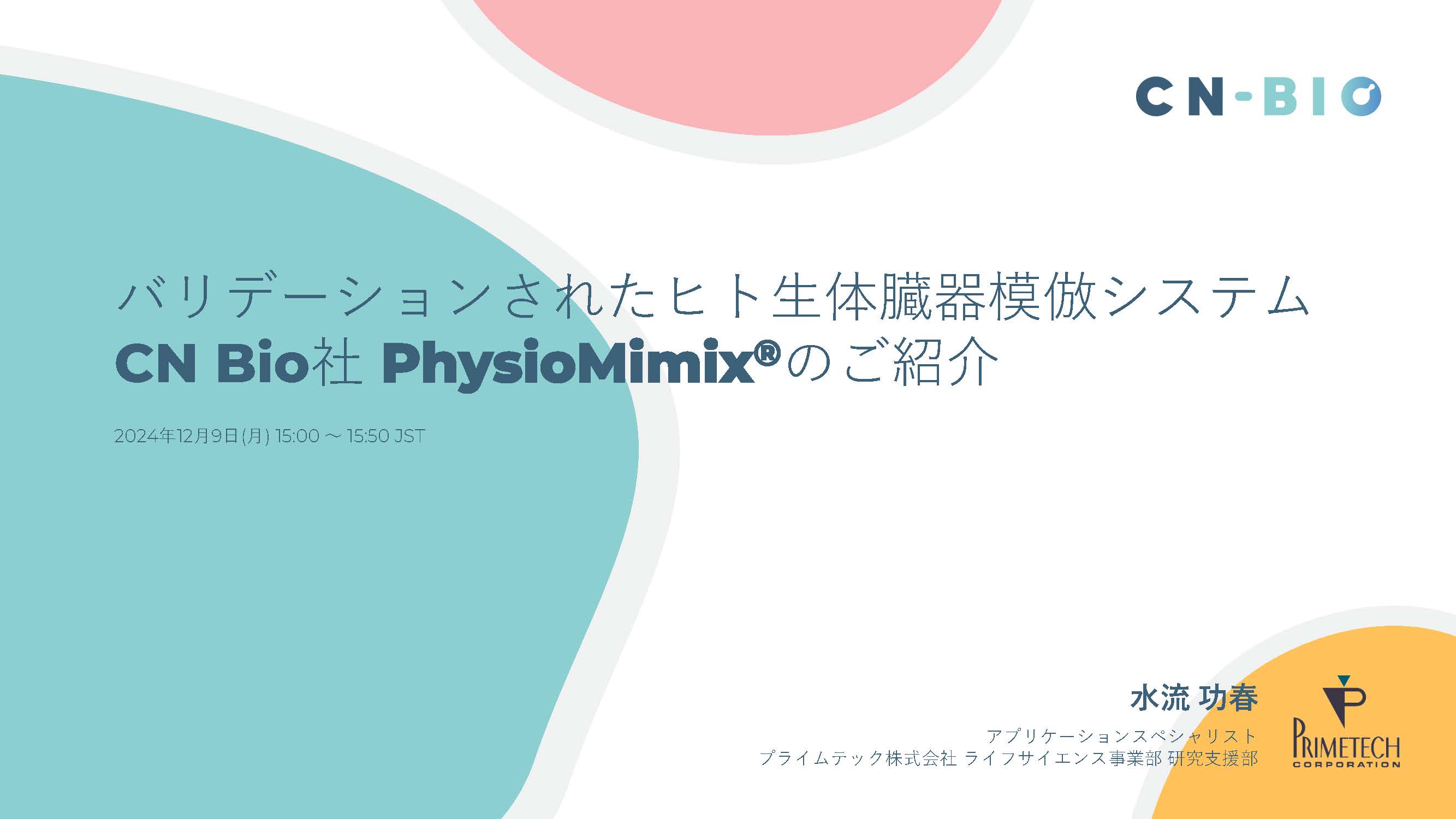
昨今の創薬研究において、以前から開発が続けられている低分子や抗体医薬、核酸医薬に加えて、細胞移植、次世代ペプチド、AIを活用した人工タンパクなど創薬モダリティは大きく変化しています。しかしながら、医薬...
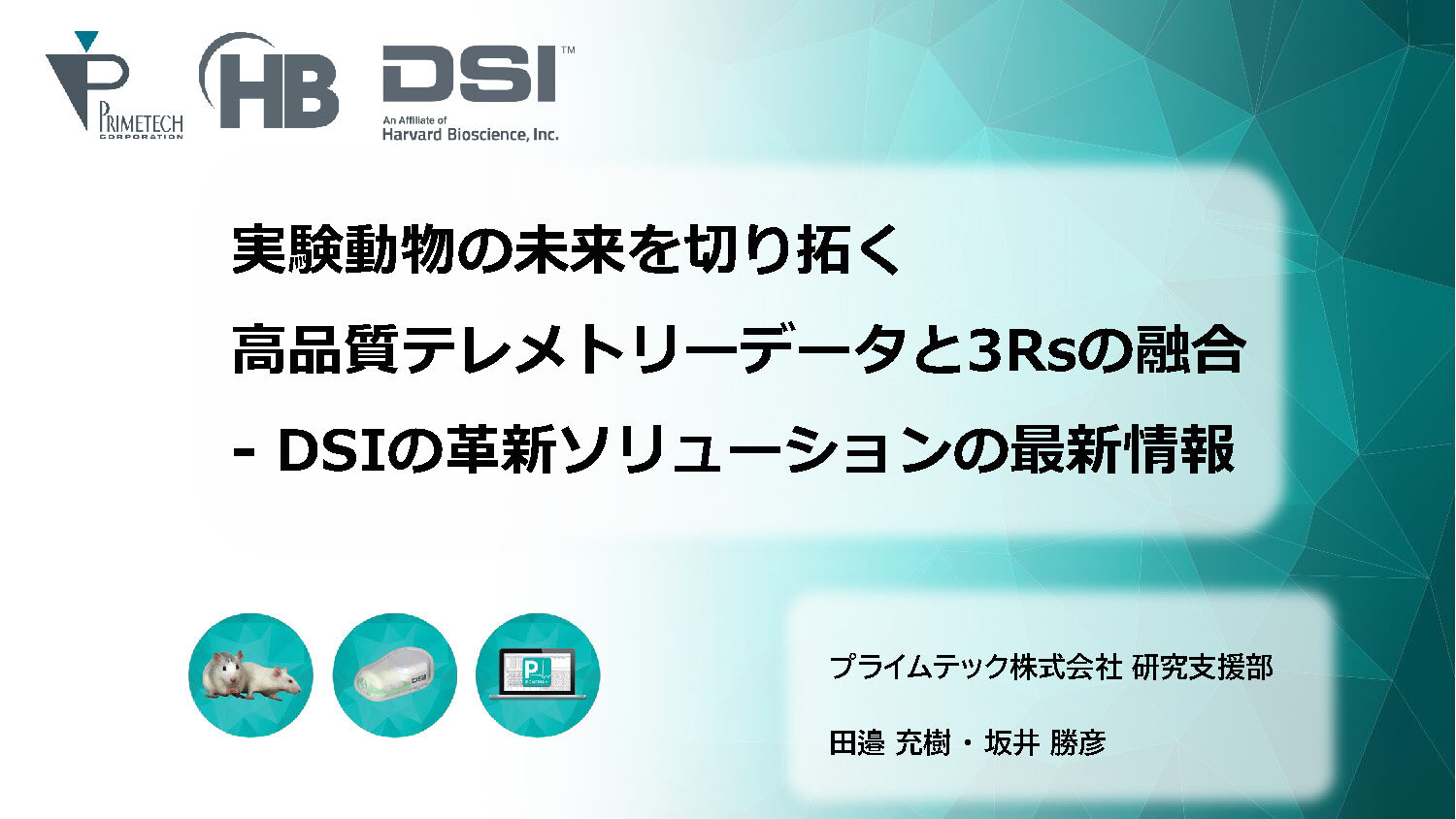
DSI (Data Sciences International)は、過去40年以上にわたり、実験動物における生理学的計測ソリューションを一貫して提供してきました。 特に無侵襲・無拘束のテレメトリー技...
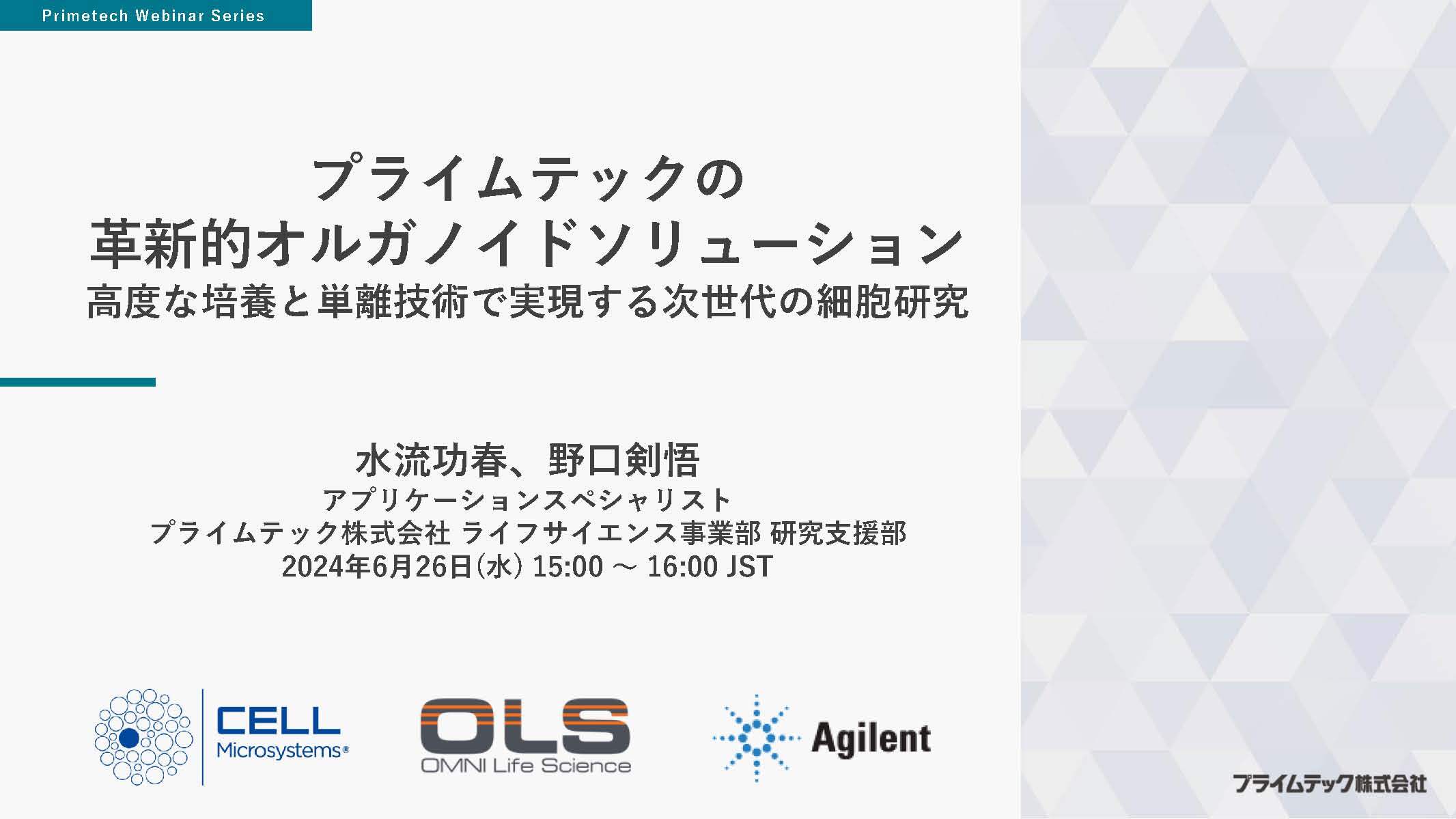
昨今の細胞培養技術の発展により、生体内環境を模倣した三次元培養技術が一般化されつつあり、細胞集団、組織構造物として形成されるオルガノイド(およびスフェロイド)の活用が進んでいます。
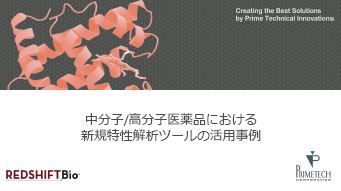
近年、抗体医薬品に代表されるバイオ医薬品や核酸医薬品の開発が盛んにおこなわれています。さらに、新たな創薬モダリティとして遺伝子治療やmRNA医薬品の上市が進められております。
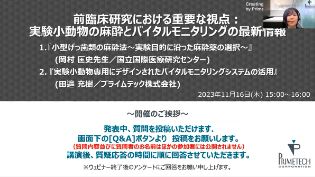
前臨床研究において用いられる実験小動物、特にマウスやラット、ハムスターといった小型げっ歯類に全身麻酔を施す際は、過麻酔や体温低下による死亡事故や覚醒後の予後不良のリスクを抑制するために、心拍数や呼吸、...
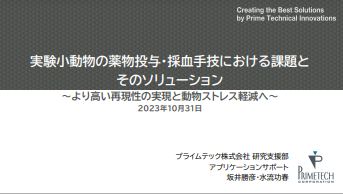
今日の創薬・治療法開発を目指した基礎研究において、マウスやラットといった実験小動物を用いた薬物投与および採血操作は、医薬品や再生医療などの基礎研究において欠かせない手法です。 しかしながら、サイズの小...
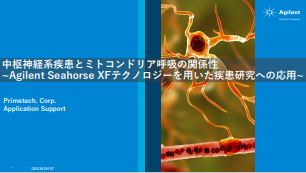
神経変性疾患には、アルツハイマー病、パーキンソン病、萎縮性側索硬化症(ALS)、前頭側頭型認知症(FTD)、レビー小体型認知症などの中枢神経系(CNS)疾患が含まれています。また、神経系の機能を維持す...

細胞生物学においてはエンドポイントアッセイを行うことが多く、ある単一のタイムポイントにおける細胞の挙動に関する結果を得ることができます。これに対し、近年、一定期間内におけるタイムポイントごとのデータを...
詳しい製品情報やご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。